VR
#自治体 #広報・PR
自治体のVR活用で地域観光を促進!注目の事例5選と成功ポイント
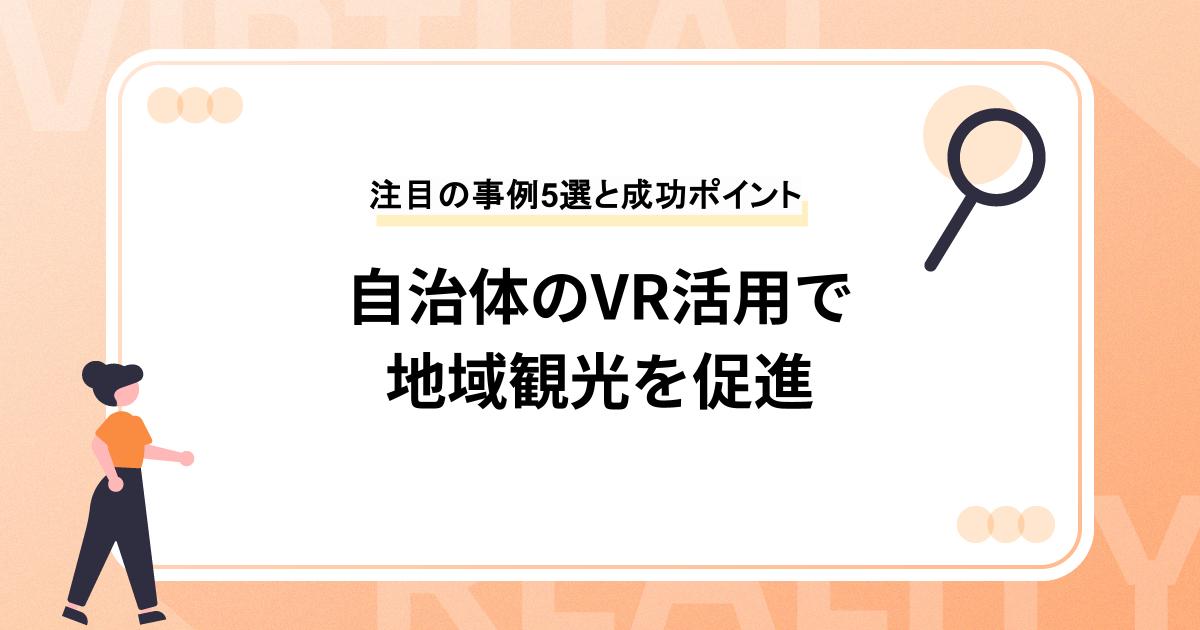
いまやエンターテイメントだけではなく、教育・医療・ビジネス・文化継承などにも活用されるようになってきたVR。実は、そんなVRを活用したプロモーションが、各自治体で活発に行われています。
今回は、なぜ各自治体がVRを使ったプロモーションを行っているのか、そのワケをお伝えします。その後、いくつか事例もご紹介します。
各自治体の広報・PR担当の方々のプロモーションの参考になればと思っていますので、ぜひ最後まで目を通していただけたら嬉しいです。
近年、自治体によるVR(バーチャルリアリティ)活用が注目を集めています。観光振興や地域の魅力発信、さらには移住促進や産業振興まで、その用途は多岐にわたります。特に観光分野では、コロナ禍以降「現地に行かなくても体験できる」コンテンツとして脚光を浴び、国内外の観光客に地域をアピールする有効な手段となっています。
本記事では、自治体がVRを導入する背景と観光への効果を整理し、実際の事例5選とともに成功のポイントをご紹介します。
1.地方がVRを活用するメリットとは?
地方自治体は、少子高齢化や若者の流出、財政悪化といった課題に直面しています。そうした中で注目されているのが「関係人口」の創出です。関係人口とは、定住者ではないものの、地域や人々と多様に関わる人々を指します。
VRは時間や距離を超えて「リアルな体験」を届けることができるため、地域外の人々に地域の魅力を疑似体験してもらい、関心や関わりを生み出す手段として有効です。観光資源を仮想空間で表現することで、「行ってみたい」「体験してみたい」という動機形成につながります。
2.VRが自治体観光に効果を発揮する4つの理由

自治体が観光分野でVRを導入する背景には、従来の観光プロモーションでは伝えきれない「臨場感」と「体験価値」を届けられるという大きな強みがあります。ここでは、自治体の観光施策においてVRが果たす効果を4つの観点から整理します。
- 地域の魅力をVRで可視化し、観光促進につなげる方法
- 地域産業のPRや物産振興への活用事例
- 観光資源そのものとしてのVRコンテンツの可能性
- 人口流出対策や雇用促進におけるVRの役割
2-1.地域の魅力をVRで可視化し、観光促進につなげる
VRは360度映像によって現地の雰囲気をそのまま伝えることができます。視聴者は自分の意思で視点を動かし、まるでその場にいるような没入体験が可能です。これにより、観光資源の魅力がダイレクトに伝わり、観光意欲を高める効果があります。
さらに、映像表現にナレーションやテキストを加えることで、単なる映像体験にとどまらず「学びのある観光体験」を提供することも可能です。実際に訪問する前にVRで地域を知ることで、観光客はより深い興味を持ち、旅行時に「ここで何を体験したいか」を明確にできます。
2-2.地域産業のPRや物産振興に活用できる
伝統工芸や地場産業の制作過程をVRで発信すれば、現地を訪れなくても職人の技術や情熱を体感できます。ECやオンライン販売と組み合わせることで、販路拡大やブランド価値向上にも寄与します。例えば、工芸品の制作工程をVRで配信し、オンラインショップに誘導する仕組みを作れば、観光客が「購入体験」を通じて地域とのつながりを深めることが可能です。地域のストーリーを映像で届けることで、単なる物販ではなく「文化を買う」という価値提供にもつながります。
2-3.VRコンテンツそのものが観光資源に
歴史的建造物や遺跡をVRで再現すれば、来訪者に「その時代を旅する体験」を提供できます。VRが一種の観光アトラクションとなり、地域の観光価値を高めることができます。特に、現存しない歴史的建造物や古代遺跡をCGとVRで復元する取り組みは、教育的価値も高く、学校や研究機関と連携することで新しい学習コンテンツとして活用できます。こうした取り組みは、観光客にとっての「知的体験」を強化し、地域滞在時間や満足度を高める効果があります。
2-4.働く現場をリアルに伝え、人口流出対策に貢献
バーチャル工場見学や企業紹介をVRで行うことで、地域の魅力ある仕事を若者に伝える取り組みも進んでいます。これにより、U・Iターン促進や地元就職のきっかけづくりにもつながります。
特に、製造業や農業、伝統産業など、現地でしか体験できない職場環境をリアルに発信することで、「この地域で働く」という具体的なイメージを醸成できます。
また、採用活動に活用することで企業の認知度向上やミスマッチの防止にも効果的です。結果として、地域の人材流出を防ぎ、定住促進につながる可能性があります。
3.VRを活用した自治体観光プロモーション事例5選
ここからは、実際に自治体がどのようにVRを観光プロモーションに取り入れているのか、具体的な事例をご紹介します。それぞれの地域が抱える課題に対し、VRをどのように活用して解決や魅力発信につなげているのかを見ていきます。
- 和歌山県北山村|「日本唯一」を届ける観光VR
- 宮崎県|伝統芸能「神楽」を伝えるVR映像
- 新潟市江南区|まちの路地をテーマにしたVR発信
- 東京都「TOHOKU × TOKYO」|外国人向けVR体験
- 群馬県高崎市|古墳タイムトラベルVR
3-1.和歌山県北山村|「日本唯一」を届ける観光VR
和歌山県北山村では、日本で唯一の飛び地というユニークな地域性をPRするため、名産「じゃばら」や600年続く筏下りをVR映像化しました。筏師の目線から体験できる迫力ある映像は、自然と共生する村の文化を体感できる貴重な機会を提供しています。
また、この映像は観光プロモーションとしてだけでなく、教育現場でも「地域学習の教材」として活用されています。2025年の大阪・関西万博でも多言語版で公開予定であり、国内外の観光客への訴求が期待されています。
■北山村(和歌山県)|観光向けVR動画 事例ページはこちら
3-2.宮崎県|伝統芸能「神楽」を伝えるVR映像
宮崎県では、舞手の高齢化や後継者不足が課題となる伝統芸能「神楽」を後世に残すため、VR技術を活用しました。「米良の神楽」「高原の神舞」「椎葉神楽」「高千穂の夜神楽」を舞手目線や客席目線など多角的に撮影し、迫力ある映像を公開しました。
これにより、神楽を知らない人にも伝統芸能の魅力を体感してもらえる仕組みを実現しています。2025年大阪・関西万博で初披露後は、オンライン配信によって国内外の人々に広く届けられる予定で、文化継承と観光振興の両立を目指しています。
■宮崎県|伝統芸能「神楽」を伝えるメタバース・XRコンテンツ 事例ページはこちら
3-3.新潟市江南区|まちの路地をテーマにしたVR発信
新潟市江南区では、観光資源が少ないという課題を逆手に取り、日常的に人々が行き交う「まちの路地」をテーマにVRを制作しました。
商店街や昔ながらの路地裏を映し出すことで、住民の生活文化を感じ取れるようなコンテンツとなっています。大きな観光名所ではなく「普段の暮らし」を魅力として打ち出すことで、観光客にとって新鮮な発見を提供し、地域に親しみを持ってもらう狙いがあります。
■YouTubeチャンネル「niigatacitychannel」はこちら
3-4.東京都「TOHOKU × TOKYO」|外国人向けVR体験
東京都が展開する「TOHOKU × TOKYO」プロジェクトでは、外国人旅行者が日本文化に触れる機会を創出するため、東京と東北の文化・観光コンテンツをVRで発信しています。
実際に旅をしているかのような没入体験を通じ、訪日外国人が短期間の滞在中でも日本の伝統や地域文化を理解できる仕組みを構築しています。観光の満足度を高めるだけでなく、再訪意欲を喚起する効果も期待されています。
■TOHOKU × TOKYO WEBページはこちら
3-5.群馬県高崎市|古墳タイムトラベルVR
群馬県高崎市では、観音山古墳や観音塚古墳を対象に、建造当時の姿を再現した「古墳タイムトラベルVR」を開発しました。現地でスマホをかざすと、当時の古墳の姿が立体的に蘇る仕組みとなっており、観光客は歴史的遺産をより深く理解できる体験が可能です。
教育現場での活用も進んでおり、歴史授業や社会科見学の一環として利用されるケースも増えています。観光と教育を両立した取り組みとして、地域の知名度向上にも寄与しています。
■群馬県の公式サイトはこちら
4. 自治体PRにおけるVR活用の未来と成功ポイント
VRは観光振興にとどまらず、移住促進、産業振興、教育、医療など幅広い分野での活用が期待されています。しかし、重要なのは「コンテンツ制作で終わらせない」ことです。
- YouTubeや公式サイトでの発信です。
- 多言語対応によるインバウンド活用です。
- 他の施策(物産展・移住フェア)との連動です。
といった施策と組み合わせることで、観光誘客効果を最大化できます。自治体の課題や目標に合った活用設計こそが成功のポイントです。
5.まとめ
「自治体 × VR観光」の取り組みは、地域資源の新たな発信手段として広がり続けています。没入感のある体験を通じて地域に関心を持つ人を増やすことは、観光振興だけでなく、地域課題の解決にもつながります。
リプロネクストでは、自治体のVR・AR・メタバース活用を企画から開発までサポートしています。「地域の魅力を新しい形で発信したい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。
▶お問い合わせはこちら