メタバース
#観光 #イベント #広報・PR
メタバースの仕様書を作るときに必ず押さえるべき10のポイント【自治体・行政向け】
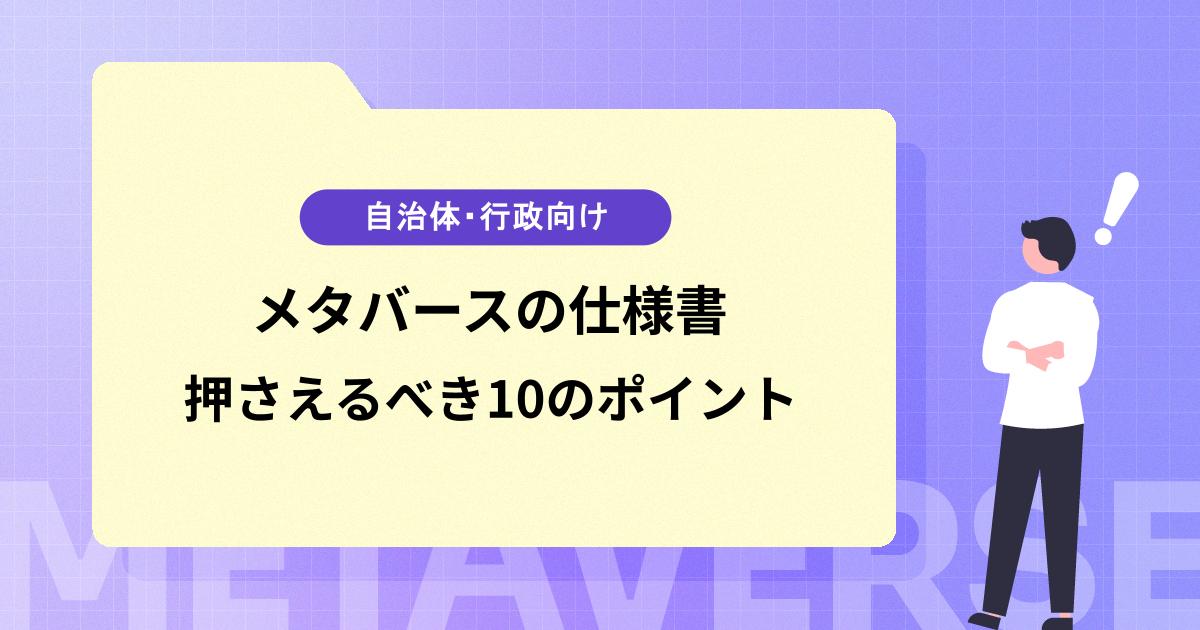
近年、自治体や企業によるメタバース活用が急速に広がり、観光振興、文化継承、移住促進、福祉支援など、行政サービスの多様な分野でデジタル空間を活用する事例が増えています。一方で、現場では「完成イメージの共有が難しい」「制作途中で仕様が変わる」といった課題が起きやすく、計画どおりに進まないケースも少なくありません。
その成否を大きく左右するのが、プロジェクト開始前に作成する仕様書(要件定義書)です。メタバースは空間・体験・運用が複合するプロジェクトのため、目的や要件を整理しないまま制作を始めてしまうと、完成後の齟齬や運用負担の増大につながります。
本記事では、自治体・行政がメタバースの仕様書を作成する際に押さえておくべき10のポイントを整理し、実務で活用しやすい形で解説します。メタバース導入を検討する自治体職員の方、入札や企画書作成で仕様定義が必要な方に向けたガイドです。
1. メタバースとは
メタバースとは、インターネット上に構築された仮想空間のことで、ユーザーはアバターを介して移動・交流・体験を行います。近年はPCやスマートフォンから参加できるブラウザ型も普及し、自治体による観光PR、移住促進、文化発信、福祉支援まで幅広く活用されています。
地方創生におけるデジタル活用は内閣府でも推進されており(出典:内閣府公式サイト)、地域課題に対して新しいオンライン接点を生み出す有効な手段として注目されています。
メタバースは、空間制作に加えて体験設計・イベント運営・データ分析など多要素が絡むため、その基盤となる仕様書の精度が成功を左右します。
2. 仕様書がメタバース事業の成否を左右する理由

2-1. 制作会社によって品質や得意領域が異なるため
メタバース制作には、3DCG、システム開発、インターフェース設計など複数の領域が関わります。制作会社ごとに得意分野が異なるため、仕様が曖昧だと「機能は満たしているが想定していた体験と異なる」という状況が起きやすくなります。
参考イメージや想定ユーザー、体験シーンを仕様書に記載しておくことで、認識のズレを防ぎ、期待値に沿った成果物へ近づけることができます。
2-2. プラットフォーム選定がプロジェクト全体に影響するため
メタバース事業には、Roomiq、Cluster、Spatial、VRChat、STYLY など、国内外でさまざまなプラットフォームが存在します。各サービスは、対応デバイスや操作性、商用利用の可否、表現できるデータ容量などに違いがあり、どれを選ぶかによって実現できる体験や運用方法が大きく変わります。
選定を誤ると、スマートフォン非対応で住民が利用できない、イベント機能に制約がある、商用利用が許可されていないといった問題が発生するため、仕様書には「どのプラットフォームを、なぜ採用するのか」を必ず明記することが重要です。
2-3. リリース後の運用フェーズが成果を左右するため
メタバースは公開がゴールではなく、イベント開催、展示更新、データ分析などの継続運用によって価値が高まります。仕様書の段階で運用体制や更新方針を明記しておくことで、リリース後の混乱を防ぎ、長期的な活用につなげることができます。
3. 成功する仕様書に共通する3つの設計視点
メタバース事業の仕様書には、目的・要件・成果物だけでなく、事業を継続的に発展させるための「設計思想」を盛り込むことが重要です。特に自治体プロジェクトでは、年度をまたぐ担当者変更や、複数部署の関与が前提となるため、企画段階での設計視点が成果物の質と運用効率を大きく左右します。
ここでは、成功している自治体プロジェクトに共通する3つの視点を紹介します。
3-1. コンセプトを「体験」として定義する
メタバース空間の制作は、建物や景観を再現する「空間づくり」が目的ではありません。住民や観光客、移住希望者など、対象ユーザーがどんな価値を得るのかという「体験価値」が中心になります。
そのため、仕様書には次のような観点で“提供したい体験”を具体的に言語化することが重要です。
・誰が利用する空間なのか
・その人は何を求めて訪れるのか
・空間に入った瞬間、どんな印象を与えたいのか
・どんなアクションを促したいのか
・体験後にどのような理解や感情を得てほしいのか
例えば、観光分野であれば「現地を訪れたくなる臨場感の高い体験」、福祉分野であれば「安心して相談できる心理的ハードルの低い体験」など、目的によって設計が大きく変わります。
仕様書に体験コンセプトを明記しておくことで、制作会社が空間デザイン、アバター動線、イベント機能などを一貫した方針で設計できるようになります。
さらに、コンセプトを体験として定義することで、完成度の判断基準が明確になり、関係者間での認識違いも防げます。
3-2. 成果物を“再利用できる資産”として定義する
メタバース制作で用いる3Dモデル、映像、音声素材などは、一度制作すれば複数の施策で活用できる重要なデジタル資産です。
仕様書では「完成物をその場限りで使う」のではなく、「他事業への横展開」「次年度への継続利用」を前提とした資産設計が求められます。
具体的には、次のような項目を仕様に含めておくと効果的です。
・3Dモデルの納品形式(fbx、glb など)
・データのポリゴン数・軽量度
・テクスチャ形式(png、jpg など)
・再利用を想定したアセットの構造
・著作権・利用権・二次利用の範囲
特に自治体事業では、同じ地域資源を別の目的でも活用するケースが多いため、資産化の視点がプロジェクトのROI(費用対効果)を大きく高めます。
例
・観光向けに制作した3Dモデルを、教育プログラムにも転用
・移住促進用の空間を、企業誘致イベントにも再使用
・文化施設の3Dアーカイブを、展示更新のベースとして再利用
「長く使える資産」として設計することは、事業継続性の観点からも重要であり、仕様書で必ず明記しておくべき要素です。
3-3. 運用と検証のプロセスを仕様書に組み込む
メタバース事業は制作して終わりではなく、公開後に運用を重ねながら成長させていくプロジェクトです。
そのため、仕様書には「運用フェーズ」までを含めて設計し、特に以下の項目を明確にしておく必要があります。
・誰が運用を行うのか(自治体/委託先/制作会社)
・更新作業はどの範囲を誰が担当するのか
・展示物やイベントはどの頻度で更新するのか
・アクセス解析はどの指標を取得・分析するか
・改善サイクルをどのように回すか
これらを仕様書に記載しておくことで、運用開始後の役割分担が曖昧にならず、担当者変更にも対応しやすくなります。
特に自治体では
・年度ごとの担当者異動
・委託期間の制約
・複数部署が関与する形態
が一般的であるため、「引き継ぎやすい構造」を仕様書に組み込むことが重要です。
また、運用プロセスを設計することで、次のような成果創出が期待できます。
・イベント内容の改善
・ユーザー属性に応じた導線最適化
・展示更新による再訪率の向上
・データ活用による事業評価の向上
運用設計は事業価値を継続的に高める基盤であり、仕様書に欠かせない視点です。
4. メタバース事業の仕様書に入れておくべき10の項目

メタバースの仕様書には、制作指示だけでなく、企画意図・対象ユーザー・成果物・運用体制まで、事業の全体像を整理することが求められます。特に自治体事業では、担当者異動や複数部署の関与が発生するため、仕様書の段階で曖昧さを残すと後工程で大きな齟齬につながります。
ここでは、仕様書に必ず盛り込むべき10項目を、実務で記述すべきレベルで解説します。
4-1. 目的
仕様書の最重要項目です。
メタバースを使って「何を達成したいのか」を明確に記述します。
例
・観光資源の魅力発信による誘客促進
・移住検討者向けの地域理解を深めるオンライン接点の創出
・匿名で相談できる福祉支援環境の整備
・地域文化のデジタルアーカイブと若年層への認知拡大
記述時のポイント
・「目的(Why)」と「手段(How)」を混同しない
・数値目標や期待される効果があれば記載
・関係部署の合意形成に使えるレベルで整理
目的が明確であるほど、制作会社は空間設計をより適切に行えます。
4-2. ターゲット
「誰がメタバース空間に参加するのか」を定義します。
対象によってプラットフォーム、操作性、デザイン方針が大きく変わるため、仕様書に必ず明記します。
例
・観光客(国内/訪日客)
・地元住民
・学生や若年層
・移住希望者
・福祉支援が必要な方
記述すべき内容
・年齢層
・利用デバイスの想定(PC/スマホ/VRなど)
・操作習熟度
・想定言語(日本語・英語・多言語対応の要否)
ターゲットが曖昧なまま進行すると、空間のUI/UXが合わず、事業の目的達成が難しくなります。
4-3. プラットフォーム
メタバースの基盤となるプラットフォームは、機能や商用ルールがサービスによって大きく異なります。そのため、仕様書には以下内容を明記します。
記述ポイント
・使用するプラットフォーム名
・選定理由(例:スマホ対応、国内利用者が多い、商用利用可など)
・商用利用やイベント開催の可否
・制作方法(ユーザー制作型/運営が制作を代行など)
・データ容量、動作負荷の目安
・アバター仕様、ワールド上限人数
自治体の入札では「プラットフォーム未選定」のまま公募されることがありますが、後の制約が大きいため、可能であれば選定方針だけでも記載することが推奨されます。
4-4. 対応デバイス
参加者がどのデバイスで利用するかは、ユーザー体験の根幹となります。
記述内容
・PC、スマートフォン、タブレット、VRヘッドセット
・OS(Windows/Mac/iOS/Android)
・推奨スペック
・VRの利用有無と必須か任意か
注意点
・スマートフォン非対応のプラットフォームは多い
・VR必須にすると利用ハードルが上がる
・自治体のターゲット層が高齢の場合は操作性も重視
仕様書に明記することで、制作会社はUI設計やデータ容量の最適化を行いやすくなります。
4-5. メタバース内で実施したい内容
メタバース空間で「何を行うか」を整理します。
この項目が曖昧だと空間設計がぼやけ、必要な機能が実現できなくなります。
想定される実施内容
・講演会、説明会、オンライン相談
・展示やアートギャラリー
・福祉相談窓口
・観光体験、文化紹介
・物販(EC連携)
・ライブイベント
仕様書に記述すべき内容
・実施したい内容の一覧
・頻度や規模(例:月1回開催、同時接続100名想定)
・必要な機能(座席、スクリーン、チャット、音声、ガイドなど)
これにより制作会社は必要な機能を正しく提案でき、齟齬が生じにくくなります。
4-6. 運営方法
公開後の運用フェーズはメタバースの成功に直結します。
記述項目
・運営主体(自治体/委託事業者/制作会社)
・運営範囲(イベント運営、展示更新、問い合わせ対応など)
・運用の内製化/委託化の方針
・運用マニュアルの要否
・サーバー管理や不具合対応の体制
自治体では年度ごとに人員が変わるため、運用内容を明確化しておくことが特に重要です。
4-7. 分析・データ
メタバースはデジタル空間であるため、アクセス解析を活用できます。
しかしプラットフォームによって取得できるデータが大きく異なるため、仕様書で明確にする必要があります。
記述例
・参加者数、リピート率
・滞在時間
・行動履歴(どのエリアを見たか)
・参加者属性(年齢、性別など)
・イベント参加数
・アンケート連携の要否
この項目を仕様書に記載することで、制作会社は分析ツールの設定やデータ取得方法を設計できます。
4-8. 公開スケジュール
公開日は制作スケジュールや制作物の精度に直結します。
仕様書に記載する内容
・公開希望日
・イベント開催日(ある場合)
・制作会社が逆算できるマイルストーン(試作提出日・最終確認日など)
スケジュールが不明瞭なままだと、制作の遅延や品質低下を招くため、初期段階での明記が重要です。
4-9. 次年度以降の活用方針
自治体事業は年度区切りで動くため、メタバースをどの程度継続させるかを仕様書の段階で整理しておく必要があります。
記述例
・次年度も運用を継続する(更新頻度を記述)
・イベントのみ実施する
・プロモーション拠点として活用する
・デジタルアーカイブとして保管する
ここを曖昧にすると、初年度の設計が短命なものになり、資産としての価値が十分に活かせません。
4-10. 参加資格
入札や公募型プロポーザルの場合は、制作会社に求める条件を明記し、成果物の品質を担保します。
記述すべき内容
・VR/AR/メタバース制作の実績数
・自治体事業の経験
・担当者の専門性(ディレクター、エンジニア、デザイナーなど)
・体制規模(プロジェクトの安定運用ができるか)
・守秘義務やセキュリティ体制
これにより、経験不足の事業者によるトラブルを未然に防ぐことができます。
5. 仕様書作成を成功させる5つのステップ(箇条書きを減らした読みやすい版)
メタバース事業の仕様書づくりは、単に要件を並べる作業ではありません。行政事業ならではの制約──予算年度や担当者異動、複数部署での合意形成など──を踏まえながら、プロジェクト全体を見通した“設計そのもの”が求められます。ここでは、自治体プロジェクトでも迷わず進められる5つのステップを、できるだけ流れを崩さず解説します。
5-1. 目的を1ページで明文化する
最初に行うべきは、事業の目的を明快に記述することです。
「誰に」「何を」「なぜ」届けるのかを整理し、事業の軸となる考えを一枚にまとめます。メタバースは空間そのものが目的化しがちですが、本来は地域課題の解決や行政サービスの改善といった“目的”が先行するべきものです。
観光であれば「訪問前の地域理解を深める体験を提供する」、福祉であれば「対面相談が難しい人でも自然に話せる環境をつくる」など、提供したい体験価値まで踏み込んで記述すると、後の工程で迷いが生まれません。
この1ページは、制作会社だけでなく自治体内の関係部署を調整する際の共通言語としても機能します。
5-2. 成果物を具体的にリスト化する
目的が固まったら、「何をつくり、何を納品するのか」を整理します。
メタバース空間、3Dモデル、写真や動画といった素材、マニュアル類、イベントの企画案など、成果物は多岐にわたります。ここが曖昧なままだと、制作途中に要件が膨らんだり、完成後に「想定した成果物と違う」といったズレが生じやすくなります。
特に自治体事業の場合、「データをどの形式で、どこまで自由に使ってよいのか」も明確にしておくことが重要です。地域資源を扱うプロジェクトでは、後年度の事業にも再活用しやすいデータ形式で整理しておくことで、デジタル資産として長く利用できる環境が整います。
5-3. 制作から公開までの工程を見える化する
メタバース制作は、空間のデザイン、機能の実装、試作品の確認など、多段階で進むプロセスです。
行政事業では決裁フローや関係部署の確認作業が一定期間必要になるため、制作会社側のスケジュールとすり合わせずに進めると、後半で時間が不足してしまうことがよくあります。
工程表には、要件のすり合わせ、試作版の提出、中間レビュー、公開前の検証といった主要なポイントを含め、どの段階で誰が確認するかをあらかじめ整理します。
特に試作(プロトタイプ)のタイミングは重要で、ここでイメージの齟齬を解消しておくことで、完成後の「思っていたものと違う」という状況を防ぐことができます。
5-4. 運用・更新計画を初期段階で定義する
メタバース事業は、公開して終わるプロジェクトではありません。
展示の更新、イベント開催、問い合わせ対応、トラブル時のサポートなど、公開後の運用が事業の成果に直結します。
仕様書には、更新を誰が行うのか、どれくらいの頻度で更新するのか、操作の難易度はどの程度か、といった運用面の設計を早い段階で記載するべきです。自治体の場合、年度ごとに担当者が変わるケースが多いため、更新作業を委託するのか、庁内で担うのか、担当部署はどこかなど、運用体制を整理しておくと引き継ぎが円滑になります。
運用計画を事前に設計することで、せっかく作ったメタバース空間が使われず終わってしまう“つくって終わり”の状態を防ぐことができます。
5-5. 将来の拡張性を考慮して設計する
メタバースや関連技術は日々進化し、要望も変化します。初年度の仕様だけで設計してしまうと、翌年度以降に機能追加がしにくくなったり、別事業で活用したい際に制約が生じる場合があります。
そのため仕様書には、未来の拡張性を前提とした設計方針を盛り込みます。例えば、展示スペースを追加できる構造にしておく、外部サービスと連携しやすい導線をつくっておく、3Dモデルを別事業でも使えるデータ形式で納品してもらうなど、資産として長く活かせる工夫が重要です。
拡張性を意識した設計にしておくことで、年度をまたぐ事業展開や他部署連携がしやすくなり、行政サービス全体のデジタル活用にも波及効果が期待できます。
6. まとめ
メタバース事業は、体験設計と長期運用を伴う行政プロジェクトであり、その成否は仕様書の精度に大きく左右されます。関係者の認識をそろえ、目的と要件を明確にし、運用フェーズまで見据えた仕様書を作成することで、より質の高いメタバース事業を実現できます。
株式会社リプロネクストでは、自治体向けメタバースの企画からプラットフォーム選定、開発、運用までを一貫して支援しています。仕様書作成や予算検討の段階からご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
▶お問い合わせはこちら