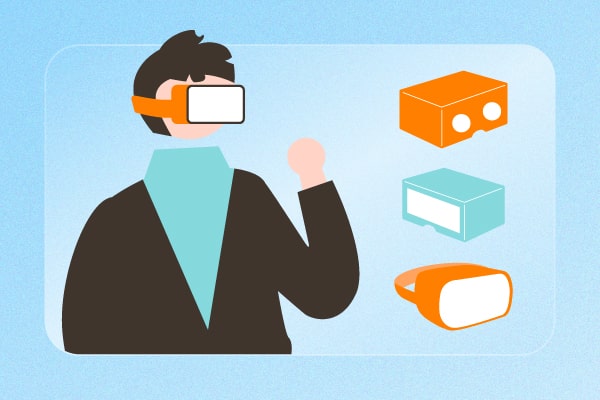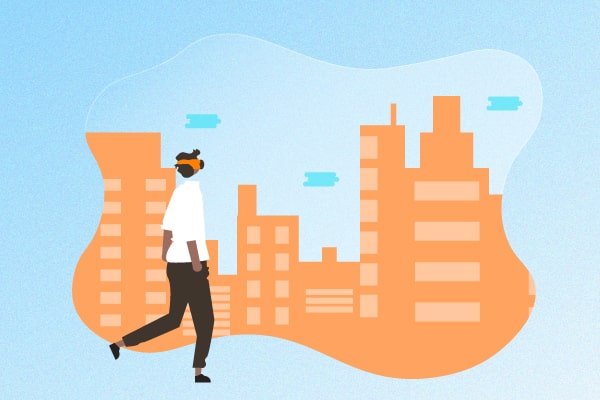- 2022/12/07
- 2024/04/11
VRって何ができる?AR・MRとの違いやゴーグルを使ってできること5選
人工知能、5G/6G通信システム、ドローンなど、めまぐるしいスピードで日々進歩するテクノロジーですが、その中でも近年多くの人々に注目されているのがVRの技術です。
調査会社IDC Japanによると、2023年のVR・AR世界市場はおよそ17兆3000億円に達すると予測されています。建設や不動産業界に並ぶ勢いで成長しているのが分かりますね。
そんなVRを「ビジネスで賢く活用していきたい」と考える方も多いでしょう。
そこで今回は、エンタメからビジネスまで幅広いシーンで役立つVRでできることをご紹介します。
また、VRのデメリットや、混同されやすい「AR」「MR」「SR」「XR」まで徹底解説いたします。
「VRを活用してみたいけど、よくわからない」「まずはVRの基本的な知識がほしい」という方は、ぜひご覧ください。
目次
1.そもそもVRとは?どんな技術?
VRは「Virtual Reality」の略で、日本語では「仮想現実」と訳されることが多いですが「virtual」という言葉がそのまま日本語の「仮想」とは当てはまらないので注意が必要です。
VRは映し出された「仮想世界」に、自分が実際に入り込んでいるような体験ができる技術のこと。
VRの歴史は意外にも長く、1968年にVR用のヘッドマウントディスプレイが開発されたことから始まりました。それから月日が流れ「VR元年」ともいわれた2016年に、各社によって大きく打ち出され、広く世間に浸透するように。それ以降、数々のVRゲームやVR動画、VRSNSが誕生しています。
では、どのように仮想世界に入り込んだような体験をさせるかというと、ユーザーの五感、主に視覚を刺激することによってそういった体験を創り出しています。現実には存在しない世界ですが、360°立体視でき、音も聞こえてきます。
どんな仕組みで映し出しているのかというと、左右の目に別々の映像を見せることで立体的に見せています。つまり、VR映像では、左目が見る映像と、右目が見る映像は少し違うということなのです。
VR映像の仕組みについて詳しい内容はVRの2画面はどういう映像か?【YouTube VRを録画してみた】の記事をご覧ください。
2.VRと似ている用語とそれぞれの違い(AR、MR、SR、XR)
VRという言葉や技術
が世間に浸透した2016年を皮切りに、〇 Rという言葉が次々と生まれています。「正直、何が何だかわからない…」という方は多いのではないでしょうか。ここでは、AR、MR、SR、XRについてご説明します。
2-1.ARとは
ARは「Augmented Reality」の略で、日本語では「拡張現実」と訳されることが多いです。ARはスマートフォンやタブレットを通じて、現実世界にCGなどで作るデジタル情報を加えるものです。
つまり、現実世界に仮想現実を反映(拡張)させる技術ということになります。スマートフォンをはじめとしたモバイルデバイスが進化してGPSやカメラを利用した高度な情報処理が可能になったことから発展した技術だといえます。例えば、スマートフォンのカメラで寿司を映すとネタの名前が映し出されるなど、見えなかった現実のものが見えるようになるというイメージです。
ARの活用事例:IKEA
大手家具メーカーのIKEAは、AR技術を使って自分の部屋に家具を試し置きすることができるアプリを配信しています。
家具を買う前に自宅に置いたらどのように雰囲気が変わるのかということを試してみることができるというのは嬉しいですね。
2-2.MRとは
MRは「Mixed Reality」の略で日本語では「複合現実」と訳されます。
MRは「現実世界と仮想世界を同時体験する」というARとVRを融合させたような技術です。カメラ付きのヘッドセットを着用し、現実世界にCGを投影するなど、ARよりもより没入感のある体験が現実世界で可能となります。
MRの活用事例:チャンギ国際空港
チャンギ国際空港の荷物積み込みにMRを活用しています。
彼らはスマートグラスを装着し、各コンテナにあるコードをスキャン。するとその場で搭載方法の確認を行うことができ、業務が大幅に効率化しました。
2-3.SRとは
「SR=Substitutional Reality(代替現実)」という概念もあります。
これは今、見えている映像と過去の映像を重ね合わせ、過去に起きたことを追体験したり、現実と編集したの映像を重ねて、未来を体験できるような技術。視覚以外にも、聴覚や触覚などさまざまな感覚を刺激して限りなくリアルに近い体験を実現します。
2-4.XRとは
XRとは「X Reality(クロスリアリティー)」。VR、AR、MR、SRのような「仮想と現実を組み合わせた新たな体験技術」を総称した表現です。
現実世界だけではなく、仮想世界、さらにはそれぞれを重ね合わせて融合する動きがある中で、個別の技術ではなくこれらを総じて「XR」と表現しています。
3.VRを体験するために必要な道具は何?

VRを体験するために必要なものは下記の2点です。
- VRゴーグル
- VRコンテンツ
ただし、VRゴーグルと言ってもMeta Quest(写真右)のような高性能のヘッドマウントディスプレイもあれば、スマートフォンで閲覧する簡易的なタイプ(写真左)まで様々です。
VRゴーグルの種類については、下記の記事をご覧ください。
▶︎▶︎VRゴーグルとは?使い方と選び方【初めてVRに触れる方は必見】
4.VRを活用するメリット
それでは、VRを活用するメリットやメリットについてもご紹介します。
まずはメリットから見ていきましょう。
- 距離・時間の制約を受けない
- リアルな雰囲気を届けられる
- 自由度の高い表現ができる
- 人件費等コストの削減
- 人数制限なく利用できる
4-1.距離・時間の制約を受けない
VR最大のメリットは、距離や時間の制約を受けず、リアルな雰囲気・臨場感を届けることができる点です。
これにより現地に行かずとも、24時間365日好きな場所から疑似体験をすることができます。
4-2.リアルな雰囲気を届けられる
動画コンテンツも非常に豊かな時代となっていますが、動画には「映っていない死角の部分」が存在します。VR映像は360°視聴者が自由に視点を動かして見渡すことができるので、本当にその場所にいるかのようにリアルな雰囲気を感じられるのが魅力です。
4-3.自由度の高い表現ができる
VRは、コンテンツによっては動画や写真を埋め込むことができます。
企業や商品の詳しい情報、伝えたいポイントをピックアップして届けることが可能になります。VR映像×2Dコンテンツで、効率的に情報を届けることができるのは、リアルではなくオンラインだからこそのメリットでもあります。
4-4.人件費等コストの削減
VRコンテンツを制作すれば、半永久的に利用していただくことが可能です。
実際に行うイベントや研修などは、開催のたびに人件費等がかかってしまいますが、VRではそれらのコストを大幅に削減して、いつでも疑似体験を届けることができます。
4-5.人数制限なく利用できる
新型コロナウイルス感染拡大により、大勢の人が集まるイベントの実施が困難となりました。
また、リアルな場で開催するイベントにはどうしても収容人数に制限が生まれ、参加希望者全員が集まることは難しいです。ですが、VRであれば、各々が好きな場所から参加することができるので制限を設けずに開催することが可能です。
5.VRを活用するデメリット
VRを活用するには、もちろん課題もあります。主なデメリットが次の5つ。
- 容量が重い
- 画質の問題
- 知識が必要
- VR酔いの可能性がある
- ながら作業ができない
5-1.容量が重い
VR360°動画を4Kの解像度で10分間撮影すると、目安としておおよそ6GB前後のデータファイルになります。通常の4K動画と比較すると、約2倍のデータ容量を使用することになります。
動画のアップロード、ダウンロード、いずれにしても大量のデータ通信が必要になるので、VRゴーグルを日常的に使用するなら、通信量無制限のインターネット環境が必須と言えるでしょう。
さらにオリジナルVRコンテンツを作成する場合は、アップロード速度が遅いと大変非効率な作業になってしまうため、光回線の契約も検討する必要があるでしょう。また通信速度の他には、動画を処理するPCのスペックも重要な要素となります。
5-2.画質の問題

視覚を最大限に利用するVRでは、画質の良不良によって映像コンテンツへの没入感が変わってきます。
例えばPSVRの解像度は1920×1080と、他のVRゴーグルと比較すると高いとは言えませんが、画面の書き換え速度を表すリフレッシュレート値が高いため、滑らかでチラつきが少ない特徴があります。
また、Meta Questは高画質かつ有機EL画面搭載なので、臨場感溢れる映像を楽しむことができるのです。
このように、どのVRゴーグルを選ぶかによって動画の見え方に大きな影響を与えます。
写真多めで動きが少ないコンテンツをメインに使用するならスマホ用VRゴーグルでOK、動きの多い3D映像をフルに使ったコンテンツならMeta Questのようなハイスペック機器がベター、用途に合わせてチョイスすることをおすすめします。
5-3.知識が必要
スマホ装着型のVRゴーグルは、簡単なセッティングで誰でもすぐに利用できるメリットがありますが、本格的なVR体験をするには力不足に感じることもあるでしょう。
美しいグラフィックで圧倒的な非現実を味わうためには、PC用VRゴーグル、スタンドアロン型VRゴーグル、PSVRなどが必須であると言えます。
しかしハイレベルなVR機器にはそれなりの基礎知識が必要になります。ソフトのインストール、外部センサーの取り付け、PC・プレイステーションのセットアップなど始めるまでにいくつかのステップを踏まなければなりません。また初心者の方で海外製品を使用する場合は、翻訳された解説を理解するのに少し時間がかかるかもしれません。
【おすすめはスタンドアローン型VRゴーグル】
「難しい設定はしたくないけど本格的なVRを体験してみたい」という方には、スタンドアローン型VRゴーグルがおすすめです。
PCの用意、外部センサーやコードの取り付け、ソフトのインストールなど面倒な準備が不要で、本体だけで気軽にVRを始めることができます。
スタンドアローン型VRゴーグルについて詳しく知りたい方は、スタンドアローン型VRとは?【おすすめHMDを一挙公開】もチェックしてみてください。
5-4.VR酔いの可能性がある
乗り物酔いと同じ原理で、VRでも三半規管が刺激されて気分が悪くなってしまうことがあります。VR体験中に起きてしまう酔いの主な原因は、ゴーグル越しに見えている世界と自分の身体の動きの間に生じる僅かなズレです。首を動かした際、画面の切り替え速度が0.02秒以上遅れて表示されてしまうと酔いやすいと言われています。
対策としては、
- 遅延の少ない高機能なVRゴーグルを使用する
- 動きに強い有機EL搭載のゴーグルを使用する
- 体調管理を意識して長時間の使用は避ける
- 激しい動きがある動画やユーザー自身が高頻度に動く必要のあるコンテンツは避ける
このような方法が考えられます。
VR酔いに関しては下記のよくある質問で詳しく紹介しています。
▶︎▶︎よくある質問:VR酔いの原因や対策方法はありますか?
5-5.ながら作業ができない

映画鑑賞やスポーツ観戦のお供に、ドリンクや軽食があると最高ですね。しかし残念ながらVRコンテンツを再生中には、ながら作業ができません。飲み食いだけではなく、誰かと話しながらや家事などのタスクをこなしながらも難しいのです。
ユーザーは目の前のVR体験に集中してしまうため、そばにいる人とのコミュニケーションが取りづらい状態となってしまいます。スムーズでストレスの少ないVR体験をしてもらうには、テキストや音声ガイダンスを活用した、1人で夢中になったとしても分かりやすいコンテンツ作り・選びが重要だと言えるでしょう。
6.VRの技術やVRゴーグルを使ってできること5選
ここではVRでできることについて5つのジャンルに分けて紹介していきます。
様々な場面で活用できるので、一つずつ見ていきましょう。
6-1.エンターテイメント

VRでできることの中で、定番かつ人気のカテゴリーといえばエンタメ。
ゲームはもちろん、VRで見ることを前提に制作された映画や、スポーツ選手や野生動物の稀少な視点を体験できるVR動画など、多くのコンテンツが流通しています。
ゲーム
VRゲームは、スマホでできるシンプルなものから、ゲームセンター・アミューズメント施設に設置された大がかりなものまで広範囲にわたって作られています。
家庭用ゲーム機では、ソニーの「PlayStation VR」とMeta社の「Metaシリーズ」が売り上げトップを争う人気機種。最新機種が続々登場し、まだまだ新しい開発が進んでいます。
動画視聴
VR専用の映画、アーティストのライブ観賞、スポーツ観戦、疑似旅行、バーチャル世界の回遊など、ここでは挙げきれないほど沢山のVR対応動画があります。
これまで動画というと、視聴側は受け身の姿勢で見ることがほとんどでしたが、VR映像であれば視聴者は見たい方向に目を向けて、その場にいるかのような体験ができるのです。
6-2.研修・トレーニング
■制作実績:長岡市IoT推進ラボ 様【きさげ技術継承VR動画】
業務で習得しなければならない工程や専門技術を、より安全で分かりやすく進めるために、VRを駆使したトレーニング教材を用いて指導することで、新人研修をスムーズに進めることができます。
研修内容を口頭やテキストだけで伝えた場合、参加者すべての人に業務内容を熟知してもらうことは難しいのが現実。しかし、実際に現場にいるかのような感覚になれるVRを使えば、理解力の個人差を縮めることが可能です。
上記のVR動画は、VRtipsを運営するリプロネクストにて制作を担当しました。後継者不足の中、伝統技術の継承、そして少しでも技術への理解を深めてもらうべく、制作したコンテンツです。
このほかにもVRを使ったトレーニングは、介護士の研修や接客マナーのレクチャーなど多くのジャンルで展開しています。共通するポイントは、一度制作した研修教材は何度も繰り返し使用することが可能なので、研修コストの大幅な削減に繋がる点でしょう。
6-3.教育・学習
VRは教育の場面でも大活躍しています。視覚と聴覚に強いインパクトを与えるVR技術を教育に用いることで、学習への向上心を高める効果が期待されています。
歴史、地理、英会話、化学などあらゆる分野でVRが活用されており、今後デバイスやコンテンツの普及が進んでいき導入ハードルが下がれば、VR教育が一般的な教育方法として認知される日はそう遠くない未来でしょう。ここでは、実際に学校教育でVRが導入された事例と、防災訓練に役立つVR教材について解説します。
学校教育
2019年9月27日、愛知県豊田市立浄水中学校では、マレーシア・フィリピン・中国の3カ国を対象にした社会科学習を行いました。内容は各国の歴史的建造物や衣装をVRで見物し、どの国の映像を覗いているのか回答していくといった授業。終了後のアンケートでは生徒全員が「楽しく、前向きに取り組めた」と回答しており、主体的な取り組みを促すとして一定の学習効果があったとされています。
▶︎▶︎引用: http://www.nttms.co.jp/news/news_kyoiku-VR.html
防災訓練
防災訓練とVRの相性は非常によくマッチしています。
従来の防災訓練ではイメージしづらかった、火災・震災の危難を脳に印象づけることが容易になります。上記の防災訓練VRでは、火災発生時にとるべき正しい行動をゲーム感覚で学ぶことができるので、子どもは関心をもって映像に集中することができます。
6-4.コミュニケーション

VRはコミュニケーションツールとしても活用できます。VRはビデオチャットと異なり、相手と通話しながら目の前の空間に文字や写真を表示させたり、ハイタッチや握手をしたりと言葉以外でコミュニケーションを取り合うことが可能です。
この新体験はソーシャルVRにて実現可能。ソーシャルVRとは、VRでできるSNSのことで、TwitterやInstagramに次ぐ新たなプラットフォームになると話題になっています。
2020年2月現在の人気ソーシャルVRは、海外では「Rec Room」、国内では「cluster」が有名です。ここでは近年ユーザー数が急上昇中の「Rec Room」について解説します。
Rec Room
Rec Roomとは、ユーザーが作ったオリジナルルームを舞台に、各々が作成したアバターを操作して自由に遊ぶソーシャルVRです。会話はもちろん、ミニゲームで遊んだり車を操作してレースをしたりと、バーチャル空間で何をするかはアイディア次第で無限大。
6-5.広報活動
VRでできることの中で、忘れてはいけないのが商品やサービスを提供する側としての使い方です。360°映像の特徴をうまく活用すれば、ユーザーの好奇心を搔き立て、企業のPR活動に良い影響を与えてくれるはずです。ここでは、実際にVRを使った広報活動の事例を紹介します。
カゴメトマトジュースの工場見学
トマトケチャップやジュースで有名な、カゴメ株式会社の工場見学VR映像です。農場で真っ赤なトマトが収穫されるシーンから、ジュースに加工されてトラックで出荷されるシーンまで、分かりやすく解説されています。
2分41秒という短い時間の中に、ありとあらゆる情報がギュギュっと詰まっている点が、VRを使ったPRのメリットですね。
小千谷市の観光PR
■制作実績:小千谷市観光交流課 様【観光プロモーションコンテンツ制作】
VRは観光PRにも大きく役立ちます。こちらは新潟県小千谷市の観光プロモーションコンテンツで、アフターコロナでの観光誘致も視野に入れ、小千谷市のリアルな魅力を国内外に向けて訴求する目的で制作いたしました。
こちらの動画では気球の試乗気分が味わえ、上空から見える雪景色と青空のコントラストを楽しむことができます。
7.VRでできることまとめ
VRでできることは、エンターテイメント分野だけでなく、教育、コミュニケーション、広報活動など盛りだくさんです。また、今後5G/6Gの通信システムが一般化すると「通信遅延の解消」「大容量データの送受信」「デバイスの同時接続可能」の3つの恩恵を受けることができます。
これにより、高画質・長時間VR動画のダウンロードやソーシャルVRなどのサービスが、現状よりもさらにストレスフリーで楽しめるようになります。
今後5G時代に入ることで、VRの技術はますます私たちにとって馴染のあるツールになるはずです。日々の生活から学びまで、暮らしを豊かにしてくれるVRの未来に、今後も期待していきたいですね。
VRtipsを運営しているリプロネクストでは、オリジナルVRゴーグルやVRコンテンツの企画・制作を行っています。法人・自治体様向けにサンプルも豊富にご用意しておりますので、ノベルティやグッズ販売にお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。